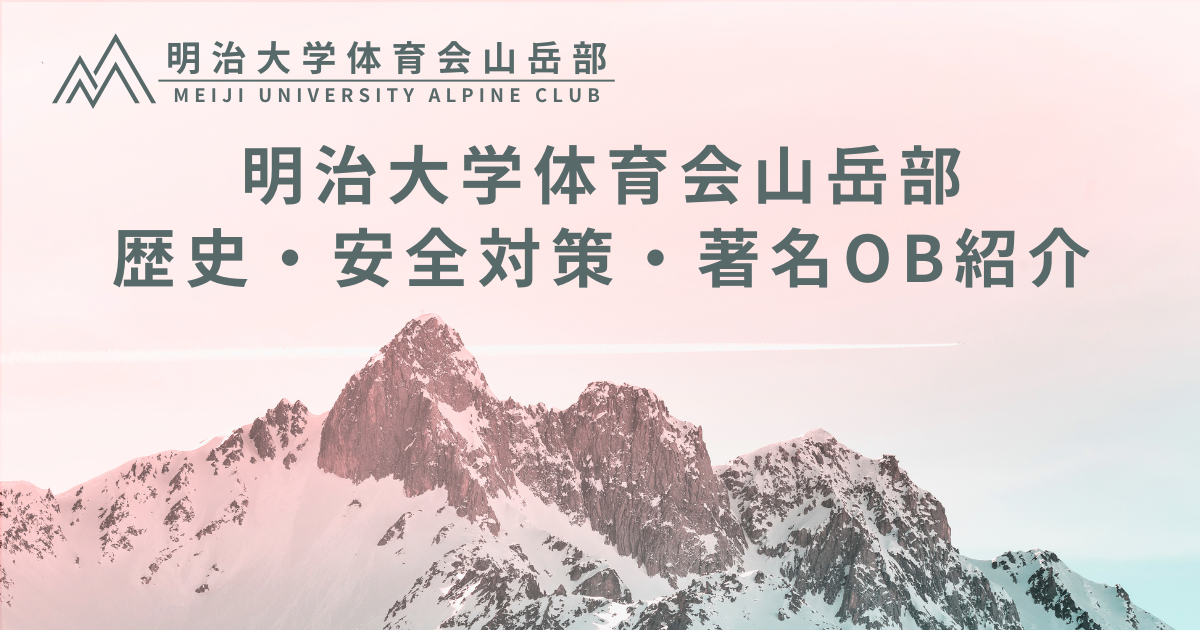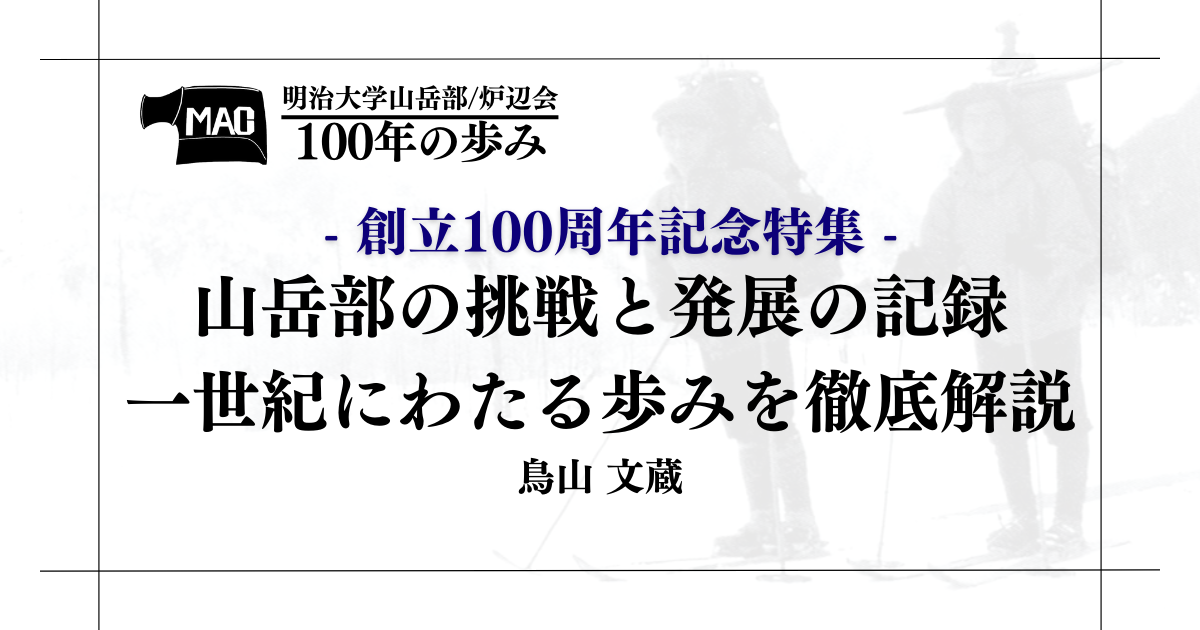明治大学山岳部の特徴
明治大学山岳部は、体育会に所属する本格的な登山部です。
とはいえ、経験者だけの集まりではありません。入部時点では未経験でも大丈夫。基礎からじっくり登山を学べる環境が整っているのが大きな特徴です。
活動は基本的に学生主体で進められていますが、必要に応じて、コーチや登山経験豊富なOBが計画のレビューや山行への同行などを行い、安全面・技術面のサポートを受けられる体制も整っています。段階的に力をつけていけるので、無理なく成長できます。
創部は1922年。100年の歴史の中で、日本人初のエベレスト登頂を果たした植村直己さんや、世界の高峰で数々の挑戦を続ける天野和明さんをはじめ、著名な登山家を輩出してきました。
また、明治大学山岳部は、一つの団体として世界の8000メートル峰14座すべてに登頂している、日本でも数少ない山岳組織の一つです。
最近では昔と異なり、授業や学業との両立もしやすい運営体制が整っており、大学生活と無理なく両立できます。山での経験を通じて、体力・技術だけでなく、計画力・判断力・チームワーク・精神力といった、生涯にわたって役立つ力を育むことができます。
4年間の大学生活を、かけがえのない時間に――。
ここでの経験が、あなたの未来を大きく広げてくれるはずです。
部長からのメッセージ
明治大学体育会山岳部では、学生が自ら計画し、行動し、山と向き合うことで、判断力や責任感、仲間との信頼関係を育んできました。
こうした経験は、現代社会――予測不能なリスクが日常に潜む「リスク社会」において、冷静な思考や柔軟な対応力を身につける貴重な学びの場となっています。
私が部長に就任して感銘を受けたのは、装備や時代が変わった今もなお、山岳部が長期縦走や極地法による冬山登山を育成の柱として大切にしていることです。2週間にわたる合宿では、食糧を担ぎ、天候の変化に向き合い、自分たちの力で自然の中を生き抜きます。
一見「時代遅れ」にも思えるそのスタイルこそが、現代人が忘れかけた体力・忍耐力・観察力を育てる最良の方法なのです。
そしてそれを可能にしているのが、「体育会山岳部」という枠組みです。登山という個人の挑戦を、組織的な教育の場にまで高めるこの体制があるからこそ、学生は仲間とともに支え合いながら、大きく成長することができます。

部の歴史と歩み
明治大学体育会山岳部は、1922年(大正11年)、明大予科山岳会とスキー倶楽部が合同して創設された「明治大学山岳会」を母体としています。この合同によって大学山岳部が発足し、翌年には学友会体育部に正式加入。ここに、現在まで続く明治大学体育会山岳部の歴史が始まりました。以降は日本全国の山々を舞台に活動を展開し、学生登山文化の黎明期を支える存在として、その名を広めていきました。
戦前には、白馬岳積雪期初登頂や剱岳八ツ峰の登攀、さらには前穂高岳北尾根への「明大ルート」開拓(1936年)など、数々の実績を積み重ね、技術と精神の土台を築いていきました。1940年には台湾での登山を実現し、初の海外登山も果たしています。しかし、1944年には戦局の悪化により活動を一時休止。戦後の混乱を乗り越え、1947年に活動を再開しました。
1950年代には、厳冬期の穂高連峰登山やマナスル登山隊への参加など、本格的な高所登山へとフィールドを広げていきます。そして1960年、創部以来の大きな節目として、カラコルムのラカポシ(7,788m)への登頂を達成。これを機に、山岳部はヒマラヤやカラコルムといった海外の高峰へと活動を広げていきました。
1965年にはヒマラヤのゴジュンバ・カンII峰(7,646m)で初登頂を果たし、以降、チューレン・ヒマール、ヒマルチュリ、アンナプルナ南峰などへも足を運び、技術と経験を重ねていきました。
特筆すべきは、OBである植村直己氏の存在です。1970年、日本人として初めてエベレストに登頂。その後も五大陸最高峰の登頂、北極点到達、厳冬期マッキンリー(現デナリ)単独行など、世界的冒険家として歴史に名を刻みました。
1980年代から2000年代にかけては、チョ・オユー、マナスル、K2といった8000m峰を次々と登り、2003年にはアンナプルナI峰をもって、世界の8000m峰14座すべてへの登頂を一つの団体として達成。この記録は、日本の大学山岳部としては他に例を見ない快挙です。
平成以降は部員数の減少などの課題にも直面しながらも、1990年代には女性部員の入部が始まり、現在では男女を問わず活動する開かれた組織へと進化。登山技術だけでなく、安全管理や体制面でも時代に応じた見直しを行いながら、持続可能な活動を続けています。
2022年には創部100周年を迎え、記念山行、シンポジウム、記念誌『炉辺11号』の発行など、多くのOB・OGとともに節目の年を祝いました。
100年におよぶ歴史の中で育まれてきた経験、技術、仲間の絆は、次の世代へ、そして次の100年へと確かに受け継がれています。山と真摯に向き合うその姿勢は、今も変わることなく、明治大学体育会山岳部の核にあり続けています。
安全への取り組み
明治大学体育会山岳部では、「安全第一」の原則のもと、無理のない計画と指導体制を整えたうえで登山活動を行っています。
活動は、年間を通じて計画的かつ段階的に構成されており、年間スケジュールは部員自身が主体となって立案します。これにより、山行の目的や準備への理解を深め、自律的に安全意識を育てていくことを重視しています。
また、山行のすべてには監督・コーチによる事前レビューと助言が入り、天候や地形、部員の習熟度に応じた適切な判断と調整が行われます。
登山技術の習得も、1年から4年まで段階的に学べるカリキュラムを導入しており、各学年の経験や体力に応じて、無理なくステップアップできるよう配慮されています。
さらに、全員が登山保険に加入しており、万が一の備えも万全です。希望者は、文部科学省の全国学生登山研修会にも参加でき、全国の大学登山者との交流や、さらなる知識・技術の習得が可能です。
学生が自ら考え、先輩・指導者の支えを受けながら、安全に、そして着実に成長していく。それが明治大学山岳部の安全登山のかたちです。
著名なMAC出身者の紹介
明治大学体育会山岳部(MAC)は、創部から100年を超える歴史の中で、数多くの登山家・冒険家を輩出してきました。部の理念である「自律・安全・挑戦」を胸に、多くの卒業生が国内外で前人未踏の山々に挑み、記録と記憶に残る偉業を成し遂げています。
その代表的な存在が、世界的冒険家の植村直己氏です。1960年代に明治大学山岳部で登山を学び、1970年には日本人として初めてエベレスト登頂に成功。その後も、五大陸最高峰登頂、北極点到達、アラスカ・マッキンリー冬季単独登頂など、前人未踏の冒険を重ね、国民栄誉賞を受賞。日本の登山文化に大きな足跡を残しました。
さらに、登山の“技術”と“精神”を極めた登山家として知られるのが天野和明氏。在学中からヒマラヤ遠征に取り組み、カランカ北壁初登攀で登山界最高の栄誉「ピオレ・ドール(黄金のピッケル賞)」を日本人として初めて受賞。現在も国際山岳ガイドとして活動し、若手登山者の育成に尽力しています。
近年では、三戸呂拓也氏がヒマラヤの高難度ルートへの挑戦で注目を集めており、精密なルート設定と確実な登攀で国内外のアルパインクライマーから高い評価を受けています。また、川嵜摩周氏は国内の岩壁・雪山を舞台に数々の困難なルートに挑み、現代アルパインの最前線で活躍を続けています。
これらのOBの活躍は、単なる記録ではなく、「学生時代の登山経験が、その後の人生の挑戦を支える力になる」というMACの精神を体現するものです。次の100年を担う現役部員たちも、その背中を追いながら、確実に歩みを進めています。
メンバー紹介
明治大学体育会山岳部は、1年生から4年生までの学生が主体となり、少数精鋭で活動する組織です。登山技術の習得はもちろん、山行の計画立案や装備の準備・管理、チーム運営に至るまで、すべての活動に学生自身が責任を持って取り組んでいます。
現在、在籍する学生部員は9名。それぞれの経験や個性を活かしながら、互いに学び合い、高め合う関係を築いています。
こうした学生の主体的な活動を支えているのが、部長の加藤彰彦(明治大学政治経済学部教授)です。山岳教育と学生支援に深い理解をもち、日々の活動に広い視野から助言をくださっています。
さらに、監督の高柳昌央氏、ヘッドコーチの谷山宏典氏をはじめとする9名のコーチ陣(いずれも明大山岳部OB)が、山行の技術指導や安全管理、装備面など多方面から現役部員をサポートしています。
それぞれの立場が互いに尊重し合い、信頼を土台としたチームとして山と向き合っているのが、明大山岳部の大きな特長です。
各メンバーのプロフィールや活動の様子は、以下の詳細ページにてご紹介しています。ぜひご覧ください。



よくある質問(山岳部Q&A)
明治大学体育会山岳部に興味を持った方から、よくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。
「初心者でも大丈夫?」「費用はどれくらい?」「勉強やバイトと両立できる?」といった不安や疑問に、現役部員の声をもとにお答えします。
- 「未経験でも大丈夫ですか?」
-
はい、安心してください!初心者向けの体制が整っており、地図読みや装備の使い方など基礎から学べます。平地トレーニングやミーティングを経て、安全に山に入れるようになります。
- 「勉強やバイトと両立できますか?
-
十分可能です!平日は週2〜3回の活動。合宿は学期中・長期休暇に調整。多くの先輩が学業と部活とバイトを両立しています。バイトについては、事前に個別にご相談ください。
- 「いつから入部できますか?」
-
年間いつでも歓迎しています!春の新歓期間以外でも見学・相談は随時受付中。公式の「新歓山行」だけでなく、先輩との個別山行やイベントから始めることも可能です。
- 他のサークルや部活との兼部はできますか?
-
原則として、兼部はおすすめしていません。体育会山岳部の活動は、週末の山行や長期休暇中の合宿など、ある程度の時間と責任が求められるため、他のサークルや部活動との両立は難しいことが多いです。
- テスト期間や就活中など、忙しいときは休めますか?
-
はい、無理のない範囲で活動できます。山岳部では、「自分のペースで継続すること」が大切だと考えています。学業や就職活動、家庭の事情など、部員それぞれの状況に配慮しながら活動を行っており、必要に応じて山行を休むことも可能です。
初めての登山・部活動選びだからこそ、安心して一歩を踏み出せるように。まずはここで、山岳部のリアルをのぞいてみてください。
まずはメールでお気軽にご連絡ください
明治大学体育会山岳部に少しでも興味を持っていただけたなら、まずは気軽にメールでご相談ください。
「登山は初めてだけど大丈夫?」「実際の活動頻度は?」「見学だけでもOK?」――どんな小さなことでも構いません。先輩部員が丁寧にお答えします。
見学や説明会のご案内も随時行っています。
山に一歩踏み出すその前に、まずはあなたの声を聞かせてください。
👇 下のボタンから、すぐにメールでお問い合わせいただけます!
\ 質問だけでも大歓迎! /