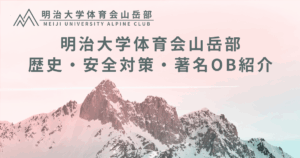明治大学体育会山岳部の活動は、学生の自主性を尊重しつつ、長年の経験と哲学をもつ指導陣の支えによって成り立っています。
登山とは、単なるスポーツやレジャーではなく、生き方そのものを問う深い営み。そんな山の本質に向き合い、現役学生たちを導く監督・ヘッドコーチ・コーチたちの想いを紹介します。
それぞれの言葉から伝わってくるのは、山の厳しさと美しさ、そして人が成長する場としての山岳部の価値。現役生はもちろん、これから入部を検討している皆さんにもぜひ読んでいただきたい内容です。
監督 高柳昌央

監督 高柳昌央
植村直己先輩がこう書かれています。
「もし、あのとき、部屋の扉を開ける勇気がなかったら、いまの僕は無かったと思っている。たった一枚の、あの重く、ススけたトビラが僕の人生を決めた。一枚開けた部屋の中には、すばらしい友達、そして僕の夢あふれる将来があった」(「部報 炉辺8号」)
何事も新しい事にチャレンジするためには最初の一歩を踏み出す勇気が必要です。
ちょっぴり勇気を出して、学生時代に山登りに打ち込んでみませんか。
山に登るルールを決めるのも、登りたい山々を決めるのもあなた自身です。
あなたの目標が人生を作り、あなたの夢を実現させる大きな原動力となります。
ぜひ、扉を開けてみませんか!
特筆すべき登山はありませんが、四季を問わず、山に登っています。特に北海道の日高山脈の山々をフィールドとしています。過去にはアフリカ、ヨーロッパ、インドヒマラヤ、シベリアなどの遠征を経験させていただきました。現在は北海道山岳ガイド協会と帯広植村直己野外学校に所属しています。
ヘッドコーチ 谷山宏典

大学山岳部で山に登る魅力って何だろうか――よくそんなことを考えます。
単独行(ソロ)ならば、いつ、どこの山に行くかを自分で自由に決められるし、行動中にほかのメンバーに気を遣ったりする必要もありません。
かたや山岳部という組織(チーム)で登山をする場合、部員同士で話し合って山行計画を決めて、監督やコーチのチェックを受けなければならないし、部員間の意見が割れれば必ずしも自分が登りたい山に登れるとは限りません。
山岳部には組織ゆえの不自由さや煩わしさがあることは事実です。それでもやはり、一緒に登る部員の存在はかけがえのないものだし、自分とは違う志向や考え方を持つ誰かとともに登ることにこそ、大学山岳部の醍醐味があるのではないかと思うのです。
私は高校時代に山を始めましたが、そのころは困難なバリエーションルートや厳冬期のアルプス、さらにはヒマラヤの8000m峰を登るなんて人生はまったく想像もしていませんでした。
けれども、大学山岳部に入って、信頼し刺激し合える仲間たちと出会い、彼らと山行をともにする中で、自分自身も成長し、山の世界も広がっていきました。
ときに厳しく、山の知識や技術を教えてくれるOBや先輩たち。互いに切磋琢磨し、つらいときは励まし合える同期の存在。世話が焼けるが、成長した姿を見ると自分のことのように嬉しくなる後輩たち。
そんな仲間たちとの登山を楽しみながら、「想像もしていなかった未来」を切り拓いていってください。
2000年
白馬北方稜線(日本海親不知~白馬岳)冬期縦走
2001年
蓮華岳東尾根〜蓮華岳
現在はフリーランスのライター・編集者として、登山関連の雑誌やWEBサイトで記事を執筆する。著書に『穂高に遊ぶ 穂高岳山荘二代目主人 今田英雄の経営哲学』『鷹と生きる 鷹使い・松原英俊の半生』『登頂八〇〇〇メートル 明治大学山岳部十四座完登の軌跡』など。共著に『日本人とエベレスト― 植村直己から栗城史多まで』(すべて山と溪谷社刊)
コーチ
高橋和弘
今でも心に残っている光景があります。
来る日も来る日も深い雪をかき分けて、ようやくたどり着いた黒部別山。
私と、そして共にここにやってきた仲間以外に誰一人存在しない世界。
目の前には夕日に照らされた剱岳が黄金色に輝き、そこに存在する音は、雪を踏みしめる足音、吹き抜ける風、そして自分の呼吸音が全てでした。
日本にこんなに美しいところがあるのか。神の存在をも感じる瞬間でした。
また、明大山岳部で登山を共にした仲間と挑んだアンナプルナ南壁、心の底から仲間を信頼し、心を一つにして巨大な壁に挑み得た頂上。
そして下山してお互いの顔を見た時に、「自分はこの世に確かに存在する。そしてこのかけがえの無い仲間と出会えて良かった」と心の底から喜びを感じました。そんな感動を味わえる部です。
遭難回避を大前提とし、真剣に登山に向き合うこの山岳部で、大学生活を誇れるものにしていきませんか。心からの感動をともに分かち合う日が来ることを、楽しみにしています。
<国内>
1995年
早月尾根-剱岳 登頂
1998年
水晶岳・赤牛岳-黒部川横断-薬師岳Ⅰ稜-薬師岳-折立
2000年
冷尾根‐爺ヶ岳‐鹿島槍ヶ岳‐十字峡‐黒部別山-三ノ窓尾根‐剱岳‐早月尾根
2005年
槍ヶ岳東稜
2007年
白萩尾根-白萩山-赤谷山-赤谷尾根(白萩尾根第2登?)
2012年
両神山麓トレイルラン 総合2位
<国外>
1995年
ガングスタン(6162m)登頂
1996年
K2(8611m)登頂
1997年
マナスル(8163m)登頂
1999年
リャンカン・カンリ(7535m)初登頂
2001年
ガッシャーブルム2峰(8035m)・1峰(8068m)連続登頂
2002年
ローツェ(8516m)登頂
2003年
アンナプルナ1峰(8091m) 南壁英国ルートより登頂
2012年
レーニア(4392m)高校生を引率、登頂
天野和明
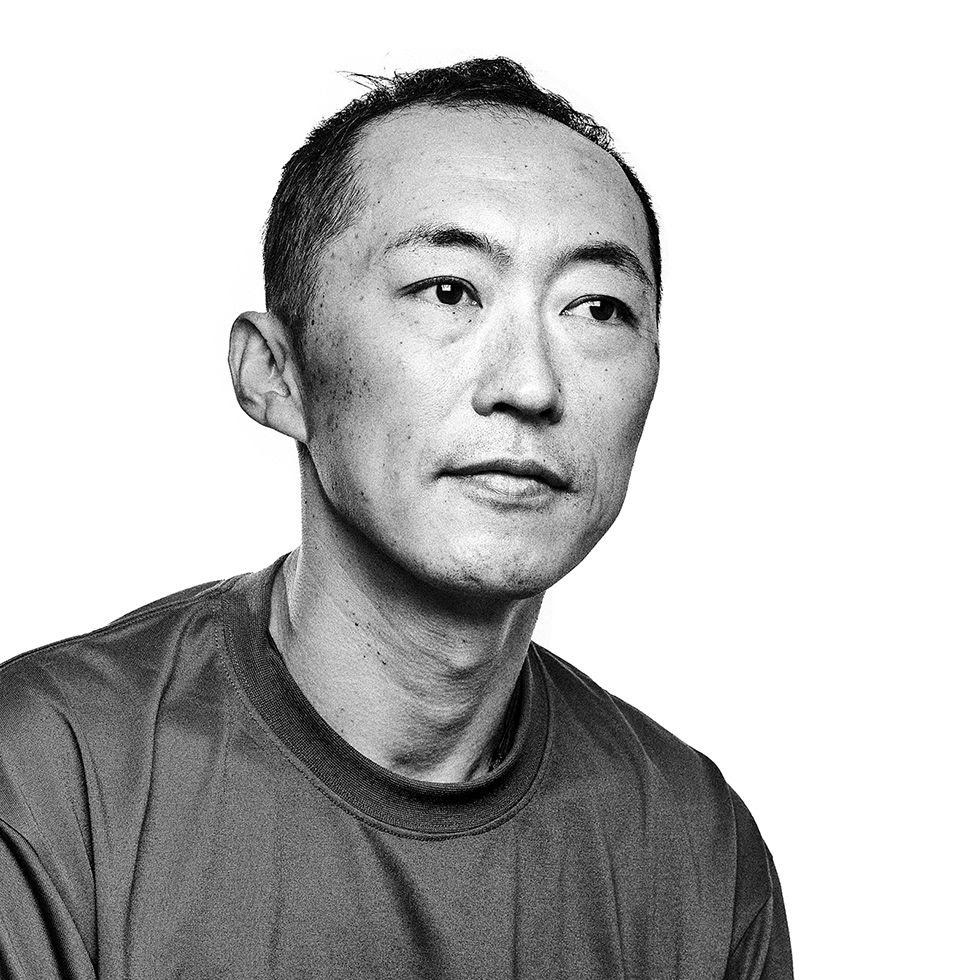
僕の山人生もここからはじまりました。
上京して山岳部の部室に入った時の緊張を今でも覚えています。
「明大山岳部は経験者も初心者も区別しない。ちゃんとした山登りをしたことがなかった自分でもできるよ。むしろ大学からはじめた部員が多いよ。」
そう言われても、本当に自分にできるのか不安も大きかったけど、覚悟を決めてやってみることにしました。
つらいこともたくさんあった(1年生の時はほとんどのことがつらかった(笑)
でも山岳部を辞めようと思ったことはありません。
一番は仲間に恵まれたから。みんなが支えてくれたからだと思います。
厳しくも愛のある先輩、同期の石田、後輩に恵まれて、4年間は山のことを考えない日はなかった。
地道だけど日本の山を季節問わずカチッと登ってきたことが基礎になり、それがその後の8,000m登山や、アルパインスタイルでのクライミングや、国際山岳ガイドとしての生活や人生につながっています。
歴史ある明大山岳部は名門といわれることもあります。
ただし、山岳部生活は決してオリンピック種目にもなるクライミング競技のように華やかではなく、重い荷物を背負ってひたすら歩く
雪をラッセルする、岩をよじ登る、氷にピッケルとアイゼンを打ち込む、それの繰り返しでじわじわと進んでいくしかありません。
でも、続けていれば必ず力が付きます。どんな人でも、やり続けていればヒマラヤに登ることは全然夢ではなく、実現可能な目標になります。
自分の思う通りにいくことだけではもちろんないけれど、伝統の力や大学、先輩方のサポートを信頼して。
大学生の時にしかできない山登りを真剣に魂込めてやってみてください。
迷わず行けよ! 行けばわかるさ!!
IFMGA認定国際山岳ガイド
石井スポーツ登山学校校長
山梨県甲州市観光大使
The North Face アスリート
La Sportiva アスリート
Blue Ice アスリート
<国内>
1996年
明大山岳部入部
1997年1月
冬山合宿 西穂高岳西尾根~槍ヶ岳まで厳冬期縦走(2年生時)
2001年7月
ガッシャーブルムII峰(8,035m)南西稜から登頂
2001年8月
ガッシャーブルムI峰(8,068m)北壁から無酸素登頂
2002年10月
ローツェ(8,516m)西壁から日本人無酸素初登頂
2003年5月
アンナプルナI峰(8,516m)南壁から無酸素登頂
2005年10月
ヨセミテ エルキャピタン タンジェリントリップなどのビッグウォールクライミング
2006年4月
チョ・オユー(8,201m)西北西稜から無酸素登頂
2006年4月
シシャパンマ(8,027m)北壁を無酸素アルパインスタイルで登頂
2006年10月
– ヨセミテ国立公園、ジョシュアツリー ボルダリングツアー
2006年11月
アマ・ダブラム南西稜 (6,812m/ネパール) 登頂
2007年3月
カナダ ポーラーサーカスなどのアイスクライミング
2008年3月
ヨーロッパ モンブランタキュル北壁、ドロワット北壁など
2008年6月
小笠原北硫黄島榊ヶ峰登頂(戦後初)
2008年9月
インドヒマラヤ カランカ(6,931m)北壁アルパインスタイル初登攀
2009年4月
スイス マッターホルン東壁ソロ
2009年7月
カラコルムヒマラヤ スパンティーク(7,027m)北西壁アルパインスタイル第3登
2010年4月
アラスカ デナリ(6,190m) 南西壁デナリダイヤモンドフリー初登攀(ルートは第6登)
2010年4月
ハンター北壁ムーンフラワーバットレス(M6)往復48時間のラウンドトリップ
2010年4月
Mt.チャーチ北壁、無名峰西壁に新ルートを開拓
2017年6月
南硫黄島に2回目の登頂
2018年6月
北硫黄島に2回目の登頂、青ケ峰戦後初登頂
2023年10月
ネパール 未踏峰アニデッシュチュリ北壁をアルパインスタイルで6,600m付近まで
<主な受賞歴>
2008年
ピオレドールアジア受賞
2009年
第17回ピオレドール日本人初受賞
石田佳岳

自由に生きることに、憧れたことはありませんか?
「自分で決めて、自分で責任を取る」それが本当の「自由」だと、私は思います。
でも私たちはつい、できない理由を環境や周りのせいにしてしまいがちです。
しかし、山はそんな甘えを許してくれません。
自然という厳しい相手と向き合う中で、自分の限界を知り・計画を立て挑み、下山し考察する。
その繰り返しの中で、「自分の責任で行動する力」が自然と身についていきます。
山岳部には、人生を自分でコントロールしていくための大切な学びが詰まっています。
ぜひ山岳部で、仲間と共に良い経験を重ね、自分の人生を、自分のものとして豊かに歩んでください。
2000年
山岳部卒部
北村昌宏

こんにちは。
いまこのページを見てくれているあなたは、きっと少しでも「山」に興味があるか、あるいは「大学生活を何か濃いものにしたい」と考えているのではないでしょうか。そんなあなたにこそ、私たち山岳部という選択肢を真剣に考えてもらいたいと思っています。
山岳部とは、ただ山に登るだけの部活ではありません。私たちが本当に目指しているのは、「人間をつくる」こと。仲間と共に計画を立て、重い荷を背負って山に入り、雨風をしのぐ幕営生活を送り、時には苦しく、時には笑いながら、自然と向き合っていく。そのすべての経験が、あなたの心と身体を鍛え、人としての芯を育ててくれます。
私は、山岳部で過ごした4年間が、自分の人生にとって最も濃密な時間だったと断言できます。挑戦の連続であり、学びの連続でした。高校までの部活動とはまったく違う、「自分で考え、判断し、責任を持つ」経験が積み重なっていくのです。4年間のうちに、人は本当に大きく変われます。自分を変えたい、もっと成長したいと思っている人には、これ以上ない環境だと思います。
また、明大山岳部には、経験豊富なOBOGの先輩方が多く関わってくださっています。長年にわたる蓄積と伝統のなかで、技術や考え方、チームとしての行動哲学がしっかりと引き継がれています。私たち指導陣も、学生と共に悩み、考え、支え合いながら、みなさんの成長を全力でサポートしています。
山で身につく力──例えば、体力、冷静な判断力、逆境に向き合う精神力、そして仲間を思いやる心──は、そのまま社会人になってからも必ず活きてきます。実際に、山岳部出身のOBOGたちは、社会のさまざまな場面でしっかりと活躍しています。登山技術やロープワークはもちろん大切ですが、それ以上に「人としての地力」が、ここでは育まれるのです。
大学4年間、何を軸に生きるか。それはあなた次第です。でも、もし「自分を変えたい」「真剣に何かに打ち込みたい」と思っているのなら、ぜひ一度、山岳部の扉を叩いてみてください。一歩踏み出せば、そこには仲間とともに歩む、かけがえのない4年間が待っています。
皆さんと山で出会える日を、心から楽しみにしています。
2007年
山岳部卒部
佐々木理人
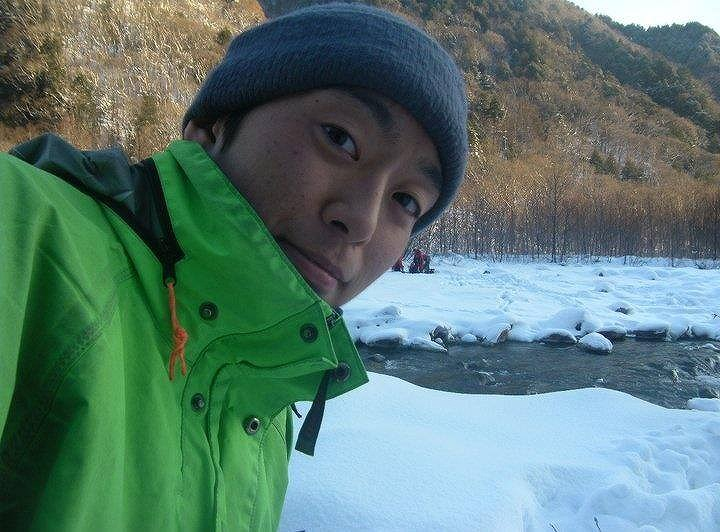
みなさんこんにちは!
大学生活では様々なこと学んで様々経験を積んでいます。
今こちらをご覧になっている方は、何かしら山岳部に興味を持って見ていただいているのかと思います。
山登り自体はとてもシンプルですが、深く知るほど歴史や分野が細かく分かれおり一つの体系をなしています。
明治大学山岳で活動しているのは、その中でも「縦走」と言われる登山が中心です。
また、厳冬期の山々を目標とした年間の活動であるため、充実感と達成感を得られることを保証します。
しかし、そのためには日々の努力が大切です。
はじめは何も分からないかも知れませんが、頑張って続けください。
山岳部に入ると学問以外の人間力が養われ、卒業後の社会での大きな自信となります。
なので、山岳部の諸先輩方は高所登山はもちろん大手企業でリーダー的な中心となって活躍される方を多く輩出しています。
2009年
明治大学体育会山岳部入部
2009年
厳冬期早月尾根 劔岳登頂
2010年
厳冬期北方稜線へ挑戦
2011年
蓮華岳東尾根より蓮華岳登頂
2011年
北米最高峰デナリ山 登頂
2012年
明治大学卒業
2012年
北アルプス無補給200km縦走
2013年
K2(8611m)へ挑戦。7000m付近で雪崩に遭遇し敗退
2015年
アイランドピーク(6160m)へ挑戦し登頂
宮津洸太郎
息を呑むような美しい山々
その別世界で過ごす非日常感
仲間と協力して手にする登頂と達成感
そういったものに惹かれ、私は山岳部に入り、今も登っています。
山には多くの危険要素が潜んでおり、それらを技術や体力、経験、チームワークなどを駆使して回避しなければなりません。
そのため活動は油断を許さず、甘くなく厳しいものになると思います。
だからこそ、決して他では味わえない充実感を、大学卒業後の生活で活きる力を、かけがえのない仲間を得られると信じています。
コーチとして、微力ながらサポートできたらと考えています。
2011年
デナリ(6190m)登頂
2015年
ジャネⅡ峰(6318m)初登頂
2018年
メラピーク(6490m)登頂
2018年
チャムラン(7319m)西稜 6500mまで
2019年
デナリ(6190m)登頂
松本拓也
川嵜摩周

私は明治大学の山岳部で登山を始めました。
全くの素人だったので、はじめはついていくのに精一杯でしたが、登山の基礎から丁寧に教えてもらい、
1年生の終わりには冬の北アルプスに登れるような力がつきました。
明大山岳部は、コーチのサポートが手厚いのが特徴です。
山に行く前の計画段階から、登山中のロープを使ったクライミング技術まで国際山岳ガイドの天野さんや経験豊富なコーチから学ぶことができます。
一人前になったら、学生だけで好きな場所へ、自由に計画を立てて登山に出かけることができるので、少しずつできることが増えていくと、やりがいを感じられると思います。
私もコーチとして、やる気ある学生の力になれたら嬉しいです。
MILLET アンバサダー
<国内>
2019年
明大山岳部入部
2020年
蓮華岳東尾根〜蓮華岳
2021年
杓子岳双子尾根〜白馬岳
2022年
赤谷尾根〜赤谷山
2023年
早月尾根〜剱岳
2024年
鹿島槍ヶ岳北壁中央ルンゼ〜
荒沢奥壁ダイレクトルンゼ継続
2024年
利尻山南稜
2025年
甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁左ルンゼ
2025年
一ノ倉沢滝沢リッジ〜
ドーム壁継続
<国外>
2023年
Anidesh Chuli敗退
2024年
Rahman Zom西壁初登
Shiyko Zom北壁初登頂



長嶺武

高校時代より登山とスキーに親しみ、2019年、明治大学体育会山岳部にスポーツ推薦で入部しました。
明大山岳部での活動は、一般の大学生活では決して得られない、かけがえのない感動に満ちています。
大学4年次には、北アルプスを中房温泉から上高地まで、いわゆるバリエーションルートで縦走した経験があります。北鎌尾根、槍ヶ岳西稜、大キレット、ジャンダルムといった、登山者憧れのルートを同期とともに踏破し、一生の宝となる思い出を刻むことができました。
山に情熱を注ぎ、心震えるような挑戦を、明治大学体育会山岳部で共に体験してみませんか。
2019年
明大山岳部入部
2020年
蓮華岳東尾根〜蓮華岳
2021年
杓子岳双子尾根〜白馬岳
2022年
赤谷尾根〜赤谷山
2023年
早月尾根〜剱岳